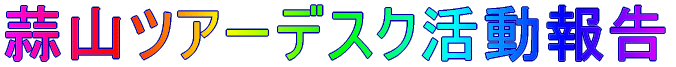
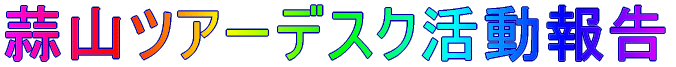 |
| 2019年12月01日~31日 | 2020年03月01日~31日 | 2020年04月01日~30日 | 2020年05月01日~31日 | ||
| 2019年08月21日~31日 | 2019年09月01日~30日 | 2019年10月01日~31日 | 2019年11月01日~30日 | ||
| 2019年08月01日~05日 | 2019年08月06日~10日 | 2019年08月11日~15日 | 2019年08月16日~20日 | ||
| 10時半出発です | 登山口です | ミヤマカタバミ |
| けなしやま でなく けなしがせん | 延齢草(エンレイソウ) | ツクバネソウ |
| 30分で五合目 | 桂の木 | もう少しです |
| 縦走参考時間 | 避難小屋より5分 | 何か咥えています |
| 沢山のカタクリの満開です | 葯は白と言うかクリーム色です | 土用ダム |
| 4月29日、調査で毛無山に登りました。雲一つない晴天の下、ユックリと歩きました。スタート時の写真でお判りいただけたと思いますが、何時もより少し多くの方が登山されていました。 鳥取県側より登山を開始され、縦走路を歩き、その後鳥取県側に下山と言う方もおられました。鳥取県より県境をまたいで他県に行くと言う事を回避なさる苦肉の登山です。お考えに頭が下がる思いでした。この様な本来あるべきと言うか、通常の登山ができないことにとても違和感を覚えます。3密でも何でもありません。ストレスを発散してリフレッシュし、免疫力を高めると罹患のリスクは下がる筈です。それどころか、ストレスまみれで免疫力が下がっていると、罹患する可能性が高まります。第2波第3波に打ち勝つ事はできません。 F1、野球、来年3月の高校野球、そして今年の開催が先延ばしになったオリンピック、たぶん難しいでしょう。国難と言う事だけで片付けないで欲しいです。決定権のあられる方は、その言葉の重みを強く認識して決断なさって欲しいです。折角の白いカタクリも多くの方に見てもら得ずに枯れてしまいます。残念です。 |
| サルメンエビネの変種 | 小枝がのしかかっています | 小枝を取り除きます |
| 昨年に比べじり貧です | 日光が当たりすぎです | 多くに小枝が・・ |
| 4月28日、サルメンエビネの保護活動を行いました。多くの個体に小枝や枯れ葉が沢山落ちかかっていました。一か所一か所確認しながら見て回ると、手を加えなくてもよい所はありませんでした。雪による、木々の被害による二次被害は少なかったですが、強風のため折れたであろう小枝が沢山のしかかっていました。 サルメンエビネの保護活動には多くのマンパワーが必要ですが、諸事情によりそれもかないません。このままではじり貧で、近い将来岡山県下で自生しているサルメンエビネは絶滅の可能性があります。岡山県下では100株位しか自生していません。次の世代にバトンタッチをする為には如何にするべきか早急に考え、そして行動しないと、取り返しができなくなると思います。決定権のあられる方は手遅れにならない内に是非行動を起こして下さい。 |
| トキワイカリソウ | 山シャクヤクの蕾 | ハシリドコロ |
| ネコノメソウ | ニリンソウ | ミヤマカタバミ |
| 崖の上のシャクナゲ | 崖の自生地 | ワサビ |
| 4月25日、恒例のワサビ採りを行いました。昨年全滅でしたので、調査を兼ねてのワサビ採りでしたが、少し復活していました。全工程を調査した訳ではありませんが、絶壁のような崖迄で止めときました。滑落の危険が高いため、本来は複数での調査がベストなのですが、今年は単独での調査となりました。 調査中色々な花を目にすることができました。中でも嬉しかったのは、シャクナゲが多くの花を咲かせていたことでした。例年ですと「ポツポツ」と咲いている程度でしたが、今年はことのほか多くの花を咲かせていました。しかし、ヤマシャクヤクは個体数が減少していました。一昨年の夏場の高温が影響しているのかも知れません。 |
| ビジターセンター前 | 登山道入り口です | 三合目 |
| 四合目 | 五合目 | 六合目 |
| 七合目 | 八合目 | 九合目避難小屋で昼食 |
| 毛無山頂上 | 尾根を降りる気流 | 雪庇の残雪 |
| カタクリ広場 | 出迎えてくれました | 白色のカタクリの蕾? |
| 白馬分岐点 | 毛無山登山口に向けて | 4時間40分で一周 |
| 4月23日、ガイド仲間三人で、カタクリと登山道の調査を行いました。昼食の時間も込めて4時間40分で一周しましたが、雪庇があった所は未だ残雪がありました。5月の連休あたりでも少し残っているのではないかと思いました。白馬のピーク辺りから雪が降り始め、見る間に白くなりました。9合目の避難小屋辺りでは零度でした。 頂上から白馬分岐点に向かう稜線沿いには数千のカタクリが自生していましたが、その多くが踏まれていました。一部を除いてロープで囲ってありませんでした。カタクリ広場は囲ってありましたが、背の低いササに覆われ、他の所よりじり貧でした。光合成があまりできないので無理もありません。休眠状態に入る前に場所を確認してロープを張って保護しないともったいないです。 駐車場で登山の準備をしている折、ご夫婦の方より「昨年リバートレッキングでお世話になりました・・」との、お話を頂きました。その折の様子が走馬灯のように蘇えり、とても幸せな気持ちになれました。ガイド冥利に尽きるとは、この事を言うのだと思いました。覚えてくださっていてありがとうございました。 |
| スノーシューも準備しています | 例年はゲートギリギリの積雪 | アオゲラが二羽 |
| トレッキング開始 | 雪が深くなってきます | 登山道のトレースは難しいです |
| この辺りで一番のブナです | ココアで温まりました | 娘さんへプレゼントです |
| 3月30日、昨日に続き、リピーターの方と烏ヶ山山麓トレッキングを行いました。つい先日までは雪はなかったのですが、烏ヶ山には雪が積もっていました。しかし、量的には中途半端。スノーシューを準備してツアーを開始しましたが、まさに「帯に短したすきに長し」で、スノーシューの出番は有りませんでした。熊除けのスプレーも出番は有りませんでしたが、熊除けスプレーは必須です。冬眠から覚めていてもおかしくありません。この辺りには3頭くらいの熊が生息している可能性があります。転ばぬ先の「熊除けスプレー」です。トレッキング開始早々、アオゲラに出会いました。途中ドラミングも聞こえました。かなり密度が高いと思います。 |
| 香川県からお越しのリピーター | 登山開始です | 尾根の切り割です |
| なだらかな道が続きます | 50分で5合目到着 | 急登の始まりです |
| 後ろのピークが頂上です | 隈笹(クマザサ)街道? | 調子が出てきました |
| ツチグリ | 分岐点 | 8合目到着 |
| この先は急登です | 2時間10分で頂上です | 後ろは湯原インター付近です |
| 下山途中の分岐点 | 田んぼの石垣 | ミツマタ |
| 足を滑らせないように | 小股で歩きます | バランスが大事です |
| 林道へ降りてきました | 逆に映っています | ユックリと5時間半で帰着 |
| 3月29日、香川県からリピーターの方をお迎えして櫃ヶ山登山を行いました。櫃ヶ山は登山道が整備されとても快適に楽しめます。櫃ヶ山では、色々な所で昔住んでおられた方の息吹を感じることができます。その様な気配を感じながらのツアーですが、色々と考えさせてくれます。時には「これで良いのか?」と、改めて問われている様な気がします。食べることへの「執念」、「命をつなぐことへの執念」が感じられます。 |
| 2019年12月01日~31日 | 2020年03月01日~31日 | 2020年04月01日~30日 | 2020年05月01日~31日 | ||
| 2019年08月21日~31日 | 2019年09月01日~30日 | 2019年10月01日~31日 | 2019年11月01日~30日 | ||
| 2019年08月01日~05日 | 2019年08月06日~10日 | 2019年08月11日~15日 | 2019年08月16日~20日 | ||
 |
|
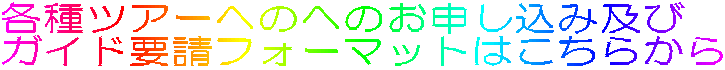 |
|